2025年秋アニメとして話題を集める『ワンダンス』。吃音症を抱える高校生と、自由に踊る少女の青春を描いた本作は、ストリートダンスをテーマにした作品として異彩を放っています。そのリアリティを支えているのが、アニメーション制作を手掛けるマッドハウス、そして世界的ダンサー・RIEHATAによる演出監修です。この記事では、『ワンダンス』の“リアルなダンス表現”を生み出す制作スタッフ陣に焦点を当て、作品の裏側に隠されたこだわりを徹底解説します。
- アニメ『ワンダンス』の制作スタッフと演出の裏側
- マッドハウス×RIEHATAが実現した“リアルなダンス”表現の秘密
- 音楽・映像・動きが融合した制作チームのこだわりと哲学
『ワンダンス』を支える制作陣とは?
アニメ『ワンダンス』が放送開始と同時に高い評価を受けた理由のひとつが、圧倒的な“リアルなダンス表現”です。観る者の心を掴んで離さないあの動きとリズムの一体感は、緻密に計算された映像演出とプロフェッショナルによる監修によって生み出されています。その中心にいるのが、名門アニメスタジオ「マッドハウス」と、世界的ダンサー「RIEHATA」。さらに、デジタル演出に強い「サイクロングラフィックス」が参加することで、従来のアニメーションでは表現しきれなかった“動く芸術”が完成しました。
マッドハウス:映像美と表現力の融合
マッドハウスは、日本を代表するアニメ制作会社の一つ。『ワンダンス』では、静止画でありながらも“動きを感じさせる”作画を得意とするスタジオの特性が最大限に活かされています。ダンスという題材は、動きの美しさやリズム感が重要な要素ですが、単に動きを再現するだけでは“リアル”とは言えません。マッドハウスが挑んだのは、“感情が動きに宿る”映像表現です。
ダンサーの動作一つ一つに、キャラクターの内面が反映されています。例えば主人公カボの初めてのダンスシーンでは、手足の震えや呼吸の速さまで細かく描写され、観る側も彼の緊張や高揚感を体感できるような仕上がりに。これらはすべて、マッドハウスのアニメーターたちが、リアルなダンス映像を何度も分析し、線の一本までこだわり抜いて描いた結果です。
RIEHATA:世界が認めたダンスディレクター
RIEHATA(リエハタ)は、日本が誇る世界的ダンサー・振付師。BTS、Chris Brown、Janet Jacksonといったトップアーティストの振付も担当しており、まさに“ダンスの女王”と称される存在です。『ワンダンス』ではダンスプロデューサー兼モーションディレクターとして参加しており、キャラクターが踊る全ての動きに彼女の監修が入っています。
RIEHATAはインタビューで「ダンスは技術ではなく感情の表現。アニメーションだからこそ、心の動きをダンスに乗せることができる」と語っています。彼女は声優の演技、音楽、リズムのタイミングをすべて合わせながら、キャラクターの“感情の揺れ”が伝わる動きを設計。ワンダの自由なステップやカボのぎこちない動きには、RIEHATAの“リアルな人間表現”が息づいています。
サイクロングラフィックス:モーションキャプチャー技術の革新
アニメーション制作で“動きのリアルさ”を追求するには、モーションキャプチャー技術が欠かせません。『ワンダンス』では、この分野に精通するサイクロングラフィックスが協力しています。実際のダンサーにセンサーを装着し、細部の動きをデータ化。その上でアニメ特有の表現に落とし込み、現実とアニメの“中間”にあるリアリズムを作り出しました。
特に、アニメ的な誇張を一切排した“自然な動き”の再現は注目に値します。動作を単にトレースするのではなく、ダンス中の呼吸・体重移動・筋肉の伸縮といった細部までモーションデータに反映させることで、まるで実写のような動きを実現しました。
“リアルなダンス”を生む演出の裏側
実際のダンサーによる動きの再現
『ワンダンス』では、アニメーション用のダンスを作るために、RIEHATAが選出した実際のプロダンサーたちがモーションを担当しました。彼らは、カボやワンダなどのキャラクターの性格や心情に合わせて、踊り方そのものを変化させています。“キャラの個性をダンスで表す”という発想は、まさにこの作品ならではのこだわりです。
ワンダのダンスは自由奔放でリズミカル。対してカボは、序盤ではリズムを掴めず身体が硬い。しかし話数を重ねるごとに、彼のステップには自信と表現力が加わっていきます。これらの変化は、モーションアクターたちが演じ分けており、視聴者が“成長”をリアルに感じ取れるようになっているのです。
キャラクターとダンスのシンクロ演出
監督の構想の中で特に重視されたのが、キャラクターの“心の動き”と“ダンスの動き”を完全にリンクさせることでした。アニメーターとRIEHATAが密に連携し、シーンごとの感情表現を共有。たとえば、カボが言葉を詰まらせる場面では、わざと動きを一瞬止めてからビートに乗る演出がされており、“言葉が止まる瞬間がリズムに変わる”という象徴的な描写になっています。
モーションデータから映像へ:制作現場のこだわり
収録したモーションデータは、サイクロングラフィックスのエンジニアによって3D化され、それをマッドハウスのアニメーターが“作画”として再構築します。ここで重要なのが、単なるトレースではなく、キャラクターの表情・呼吸・視線を後から加えていく工程。まさに“技術と感性の融合”です。
このプロセスを監督は「ダンスを“アニメーションの言語”に翻訳する作業」と表現しています。最終的な仕上がりでは、動きの正確さと感情表現が完全に一体化しており、観る者に強い没入感を与えます。
音楽と映像が織りなす“リズムの一体感”
BE:FIRSTとELSEEが紡ぐ音の世界
『ワンダンス』の音楽は、作品の心臓とも言える要素です。オープニングテーマ「Stare In Wonder」はBE:FIRST、エンディングテーマ「Wondrous」はELSEEが担当。どちらもストリートカルチャーに根差したグルーヴ感と、青春の儚さを内包した楽曲で、作品の世界観と見事にマッチしています。
特にBE:FIRSTの楽曲は、ダンスのリズムと密接にシンクロしており、アニメーションのテンポを決める“基準音”として機能。RIEHATAも楽曲制作にアドバイスを提供し、“音楽がキャラを動かす”構造を作り上げています。
Yaffleによるサウンドデザインの妙
劇中音楽を手掛けるのは、音楽プロデューサーのYaffle。彼が作り出すサウンドは、ジャズ、ヒップホップ、エレクトロニカを融合させた独自のリズム構成で、ダンスの躍動感を最大限に引き立てます。特に印象的なのは、無音とリズムの切り替えを利用した“静と動”の演出。カボが吃音に苦しむシーンでは音を削ぎ落とし、彼が踊る瞬間に音が爆発する――まさに感情を音で描く設計です。
ダンス×音楽=感情の可視化
音楽と映像がここまで密接に連携している作品は珍しく、視聴者はまるでライブステージを観ているかのような臨場感を味わえます。音と動きが感情を可視化する――それが『ワンダンス』の根底にあるテーマです。
監督・スタッフのコメントから見る制作哲学
「ダンスは言葉より雄弁」――監督の想い
本作の監督は、「吃音というテーマを扱う以上、言葉で説明するより“動き”で語りたかった」と語っています。ダンスは言葉の代替ではなく、心の表現そのもの。だからこそ、セリフを最小限に抑え、動きの中に感情を込める演出を意識したといいます。
アニメーション制作現場の挑戦と情熱
マッドハウスのスタッフは、1秒24コマという膨大なフレーム数の中で、ダンスの「間(ま)」を大切にしています。通常のアクションアニメでは省略されがちな“ステップの余韻”や“呼吸のリズム”を丁寧に描くことで、現実の動きを超えたリアリズムを実現しています。
RIEHATAが語る“踊るキャラクター”への魂のこもった指導
RIEHATAはキャラクターごとにダンスの表現を細かく指導し、「彼らの感情がどこにあるのか」を俳優的な視点で分析しています。ワンダの動きは常に“上向き”のエネルギーを持ち、カボは“内に向かう”動きから“解放”へと変化していく。このダンスの成長こそが、キャラクターの心の物語そのものなのです。
まとめ:『ワンダンス』が描く“動く芸術”の舞台裏
アニメ『ワンダンス』は、マッドハウスの精密な作画、RIEHATAのダンス哲学、そしてYaffleの音楽設計が融合した、“動く芸術作品”と呼ぶにふさわしい一作です。吃音というテーマをダンスで表現するという挑戦的な試みを成功させた背景には、スタッフ全員の真摯な姿勢と情熱がありました。
ダンスを“見せる”だけではなく、“感じさせる”映像表現。音楽、声、身体表現が一体となって描かれるこの作品は、まさに新時代のアニメーションです。マッドハウス×RIEHATAという奇跡のコラボレーションが生み出した『ワンダンス』は、これからの表現の可能性を広げる一歩となるでしょう。
- 『ワンダンス』はマッドハウスとRIEHATAによる本格的なダンス表現が見どころ
- 実際のダンサーの動きをモーションキャプチャーで再現し、感情まで映像化
- 音楽・映像・声の演出が一体化し“動く芸術”として完成
- 制作陣の情熱と技術が新時代のアニメ表現を切り拓く
- リアルとアニメの境界を超えた“心で感じるダンス作品”

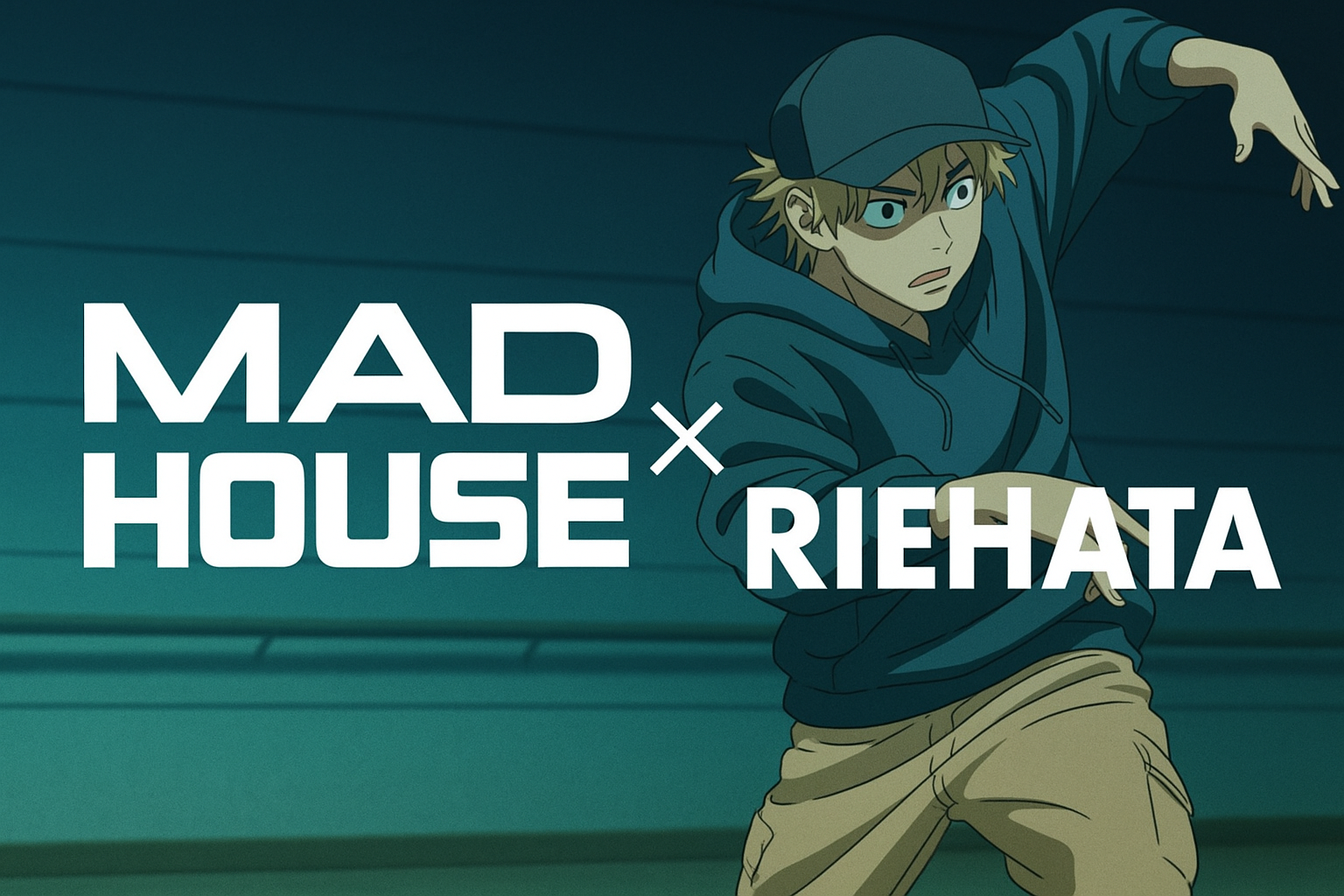


コメント